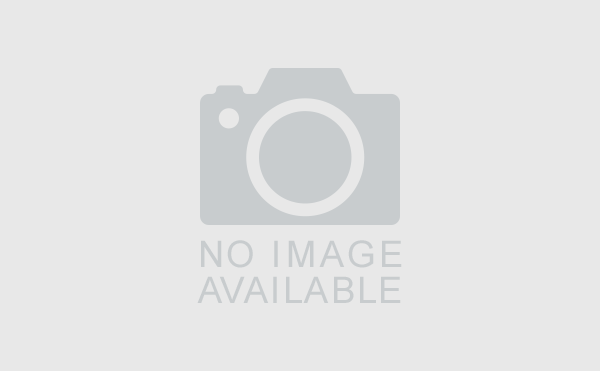俳句の作り方 下萌したもえの俳句
下萌ぬ人間それに従ひぬ 星野立子 ほしのたつこ
したもえぬ にんげんそれに したがいぬ
下萌したもえ が春の季語。
「早春、去年の枯草に隠れるように草の芽が生え出ること。
下萌の下は枯草の下の意。
下萌には確かな春の訪れと厳しい冬を耐えた生命力が感じられる。
【文学での言及】
春日野の下萌えわたる草の上につれなく見ゆる春の淡雪
源国信『新古今集』」
(ネットきごさい歳時記より)
下萌ぬ人間それに従ひぬ
句意を申し上げます。
冬枯れの草の下に隠れるように草の芽が生えました。
人々もそれに従うのです。
鑑賞してみましょう。
下萌ぬの「ぬ」は完了を表す助詞。
従ひぬの「ぬ」は強調を表す助詞です。
つまり作者はすでに生えた草の芽を見ています。
そしてそれに人間が従うというのは作者の想像であり考えです。
きっと人もそれに従うのだという強い信念です。
それでは「それ」とはなにでしょうか?
下萌えは「厳しい冬を耐えた生命力」そのものです。
まさしく大自然の命の摂理なのです。
人間にもその摂理があてはまります。
困難が人を強くするのです。
困難に向かって物事を解決しようとする人を、自然は強くします。
それは自然法則です。
人も草の芽も命あるものなので自然法則にしたがうのです。
下萌ぬ人間それに従ひぬ