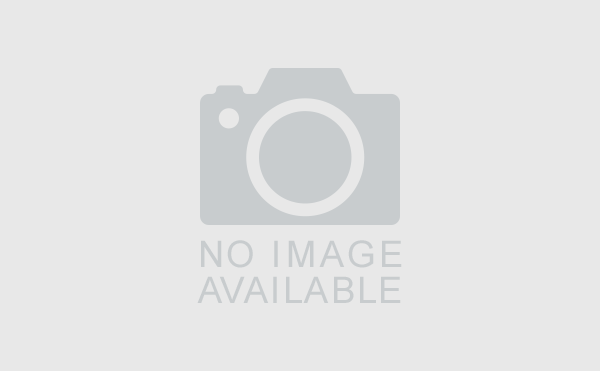俳句の作り方 鞦韆しゅうせん の俳句
鞦韆は漕ぐべし愛は奪ふべし 三橋鷹女みつはしたかじょ
しゅうせんは こぐべしあいは うばうべし
(鞦韆はブランコの事です)
鞦韆が春の季語。
「古代中国の北方民族の間では冬至後105日目に火を使わないで食べる寒食が行われていました。
その際に宮女きゅうじょたちが鞦韆に乗って遊ぶ風習がありました。」
(よくわかる俳句歳時記 石寒太編著)
句意を申し上げます。
鞦韆しゅうせん は漕ぐがよろしい。
愛は奪え。
「べし」の意味を並べてみましょう。
1⃣ 推量 きっと・・・だろう
2⃣ 意志 (必ず)しよう
3⃣ 可能 ・・・できる
4⃣ 適当、勧誘 ・・・するのがよい
5⃣当然、義務、予定 当然・・・すべきだ
6⃣命令 ・・・せよ
漕ぐに接続している「べし」は4⃣、漕ぐのがよい。
奪ふに接続している「べし」は6⃣、奪え。
鑑賞してみましょう。
鷹女51歳の句です。
当時は女性の権利が拡大しつつあるときです。
鷹女は若い世代に𠮟咤激励する意味で、愛は奪えと表現したのかもしれません。
しかし筆者は掲句は自己肯定の意味があると考えます。
鷹女が今までしてきた恋愛には既婚者を対象にしたものがあったはずです。
独身時代、既婚者の彼とお酒を飲んだ帰り、とある公園のぶらんこを目にしました。
ふらっと、ぶらんこに近寄りました。
ぶらんこに座ると彼の笑顔が思い浮かべられました。
少し漕ぐと心の声が小さく「奪え」とつぶやきました。
気持ちが良くなってさらに漕いでいくと大きく揺れました。
すると「奪え」と叫んでいました。
そんな時あの句が生まれたのです。
鞦韆は漕ぐべし愛は奪ふべし