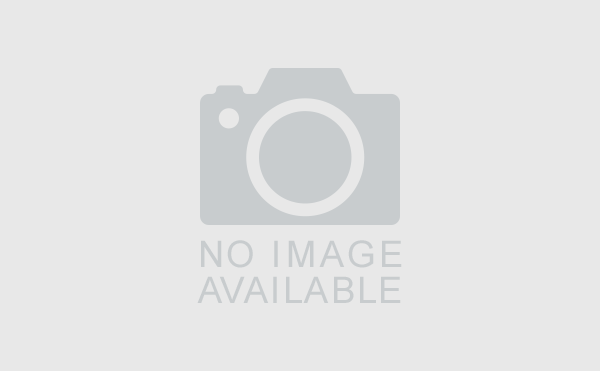俳句の作り方 端居はしゐ の俳句
いふまじき言葉を胸に端居かな 星野立子ほしのたつこ
いうまじき ことばをむねに はしいかな
端居が夏の季語。
「涼しさを求めて縁側などでくつろぐことを端居といいます。
大きな意味では納涼すずみ に含まれますが、端居は家屋の中の端近くに居る事。」
(よくわかる俳句歳時記 石寒太編著)
いふまじき言葉を胸に端居かな
いふまじき言葉を胸に端居かな
句意を申し上げます。
言ってはいけない言葉を胸に秘めながら端居をすることだなあ。
鑑賞してみましょう。
ここでの「まじ」の助動詞は禁止を意味します。
いふまじきは言ってはいけないとなります。
さて、言ってはいけない言葉とはどんなものなのでしょう?
星野立子の胸の中を覗いてみましょう。
今、作者は句会から帰ったばかりです。
あの女が鈴木に気があることは前々から分かっていた。
鈴木が桔梗が好きで幾鉢も育てていることを知ってからは、帯に桔梗の花を咲かせている。
ああ嫌だ。
問題は鈴木が作った駄句に彼女が特選を与えたことだ。
句会は作者名を伏せて皆の句が披露され互選される。
桔梗の駄句が、鈴木の作ったものかどうかは選句の時には分からない。
でも鈴木が桔梗を愛していることはみんな知っている。
〈息を吞む五尺の桔梗真白にぞ〉
この句鈴木の作に他ならないとみんな思ったに違いない。
でも秀逸はおろか佳作にも選ばなかった。
「息を吞む」が蛇足だ。
背の高い桔梗が真っ白で美しかったのは分かる。
でも、「息を吞む」が必要だろうか?
美しかったので息を吞んだわけで説明してしまっている。
こんな駄句を彼女は特選に選んだ。
公私混同もはなはだしい。
こんなことは句会では言えない。
ああ、夕立の後の風が涼しい。
いふまじき言葉を胸に端居かな