俳句の作り方 霧の俳句
なほ母をうしなひつづけ霧ぶすま 櫂未知子かいみちこ
なおははを うしないつづけ きりぶすま
霧が秋の季語。
「水蒸気が地表や水面の近くで凝結し、大気中に煙のように浮遊しているものをいう。
古くは霞かすみと霧きりに春秋の区別はなかったが、平安時代以降春は霞秋は霧と呼び分けるようになった。」
(俳句歳時記 秋 角川書店編)
なほ母をうしなひつづけ霧ぶすま
なほ母をうしなひつづけ霧ぶすま
句意を申し上げます。
相変わらず母を失い続け濃く立ち込めた霧によって母の姿が見えないなぁ。
鑑賞してみましょう。
掲句の「母」は母の愛と読み替えると解りやすくなります。
私(作者)は母の愛を求め続けています。
けれども母は私に依然として愛を注いでくれません。
濃く立ち込めた霧ぶすまが、まるで母の愛を遮って見えなくしているようです。
この句はせつない。
何故なら母性は幻想だからです。
幻想を追い続けることのはかなさがこの句には表現されています。
筆者の母も不倫をしていました。
12年間の不倫。
その間に愛された記憶はなく、虐待された記憶があります。
櫂未知子かいみちこ氏も辛かったでしょう。
筆者としては大いに共感する作品なのです。
同氏の作品にはこんなものがあります。
子は母を選べず雪の中に待つ。
夫はこんな女と結婚したのは失敗だったと言えますが、
子はこんな母から産まれたのは失敗だったとは言えません。
不倫は悪です。
家族を傷つけます。
さらに言うなら夫の子に愛を感じる事ができないので、不倫は悪なのです。
なほ母をうしなひつづけ霧ぶすま
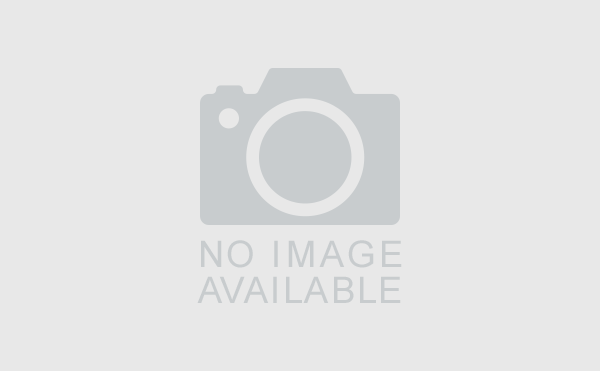
良い句ですねぇ。
確かに母性は幻想かも知れませんが、女性より男性の方が強く母性に憧れるのだと思います。
もう、50年前の私が東京に住んでいた時に、通り魔の包丁から自分が犠牲になって男の子を助けた母親の事件がありましたが、
その時母親の愛は強いんだな、と強く感じた事を思い出しました。