俳句の作り方 鶴の俳句
鶴啼くやわが身のこゑと思ふまで 鍵和田のぎへんに由に子かぎわだゆうこ
つるなくや わがみのこえと おもうまで
鶴が冬の季語。
「日本で繁殖しているのは『丹頂』1種だけで『鍋鶴』と『真鶴マナヅル』は
鹿児島県や山口県に冬鳥として渡ってきます。
その大群の中にまれに『袖黒鶴』『姉羽鶴』『黒鶴』が迷鳥として混じります。
鶴は容姿端麗な姿から古来、霊鳥やめでたい鳥として大切にされてきました。
一般に亀とともに長寿とされていますが、鶴の寿命は30年ほどと考えられています。」
(よくわかる俳句歳時記 石寒太編著)
句意を申し上げます。
ああ、鶴が啼いている。
私(作者)の声と思うまで盛んに啼いている。
鶴啼くやわが身のこゑと思ふまで
鑑賞しましょう。
あの鶴の声は私の声なのです。
何かを求めて何かが欲しくて啼く鶴の聲。
それは私の声なのです。
私もあんなに啼いてみたい!
でも私は何を希求しているのでしょう?
なにが欲しくて啼いてみたいと思うのでしょう?
ああ、私の魂は枯渇しています。
この渇きを癒すものが見当たりません。
心の渇きを潤そうとはるばる北海道にやって来ました。
凍える大地で寒さに震えながら懸命に鶴の声を聴いています。
けれども欲しいものが与えられません。
ただ鶴が啼いているだけ。
鶴啼くやわが身のこゑと思ふまで
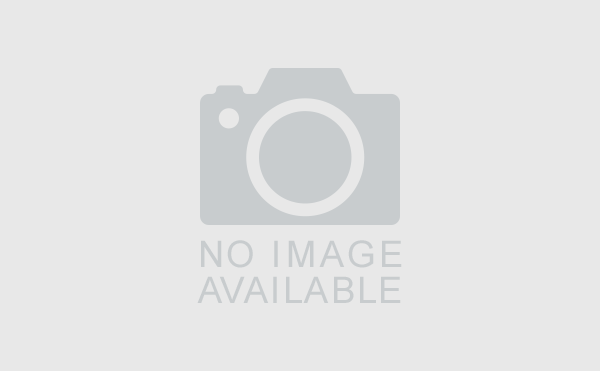
己の癒されない魂を鶴啼くに同化させた俳句。立ち姿も凛とした良い句だと思います。
この作者は伊庭さんによって始めて知りましたが、句作りに手馴れた俳人の様な気がしました。
唯、これはあくまで私の私見ですが、私は出来過ぎた句より何方かと云うと無骨な句に魅かれます。