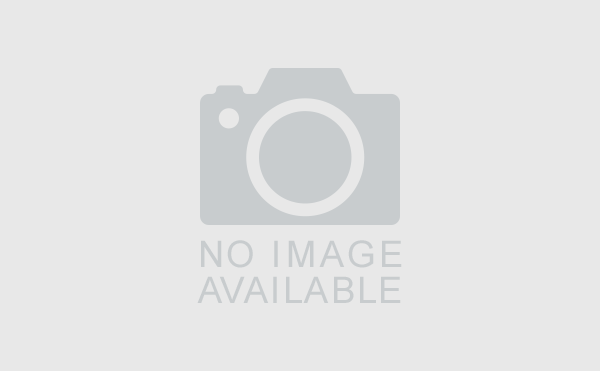俳句の作り方 端居はしゐ の俳句
端居せるこころの淵を魚よぎる 野見山朱鳥のみやまあすか(男性)
はしいせる こころのふちを うおよぎる
端居が夏の季語。
「室内の暑さを避けて、縁先や風通しの良い端近はしぢか に
座を占め涼をとることを言う。」
(俳句歳時記 夏 角川書店編)
端居せる心の淵を魚よぎる
端居せるこころの淵を魚よぎる
句意を申し上げます。
その前に「端居せる」の品詞分解をしたします。
①せ・サ行変格活用動詞「す」の未然形。
②る・継続、存続、完了の助動詞「り」の連体形
つまり端居をしつづけていると心の淵を魚がよぎる心地がすると作者が言ってます。
これでは何のことかわかりません。
作者の気持ちになって鑑賞してみましょう。
鑑賞。
涼しくて心静かに座っていると、ふと心の奥底に思念が生まれて消えました。
師の高浜虚子先生とは良好な人間関係を築きながら
先生の謳う客観写生の理念から離れて心象俳句を作ってきました。
これからも心象詠を続けていきたい。
でも体力が句作に耐えられるかどうか心配です。
結核を患って床に臥せる時間の長い私。
肝臓も悪くなってきているし・・・。
いつまで生きられるか分からない。
いや、命の長さは問題ではないのです。
一句一句に永遠の命に触れようとする詩精神が表現されていれば!
端居せるこころの淵を魚よぎる